専科-3ステップ(3):
ギターの特殊奏法・タンゴのリズムの作り方
フレーズの形(フォルム)を作るには?
曲というのものが一つの「文章」だと考えると、「段落」に匹敵するのが『楽節(がくせつ)』であり「文節=一区切(ひとくぎ)りにあたるのが『フレーズ』です。
曲を構成する「楽音」の1音1音が表情を持つのと同じように、その小さなまとまりである各フレーズにも「フレーズの表情」があります。
この「タンゴ」の場合は4小節で一つのまとまりになっています。これをワンフレーズとしましょう。
そうすると第1フレーズは「ゆったり」とした感じ、第2フレーズは「ドラマチックな激しい」感じという具合になります。
もちろん人によっては違うように感じる場合もありますが、だいたいにおいて上記のように感じることと思います。
実際に作曲者のタルレガの楽譜上の指示を見ると、演奏者が特に意識して表現しようと思わなくても、そうなるように指定されています。
第2フレーズはタンボーラとラスゲァードという弾き方の指定がしてありますから、何も考えなくてもこのフレーズは力強い感じ(フォルテ)で弾くということは想像できます。
つまり、演奏者にとって「分かり易い曲」であると言えましょう。
音楽を聴く人(勿論その第一の人物は演奏者自身)の心理としては、一本調子の表現を聴いていると退屈をしてしまいます。
聴衆を飽きさせないためには「程よい変化」が必要です。
この場合、第2フレーズが「強い(フォルテ)」フレーズですから、当然第1フレーズでは「強くない」フレーズであると程よい感じになります。
ではピアノの音量で弾けば良いのかというとそうではありません。
これが演奏の難しいところですが、「 p (ピアノ) ・ f (フォルテ)」の感覚というのは相対的に感じるものであって、演奏者の「音作りの意識」とずれることがあるのです。
つまり、この曲の場合だと第1フレーズを形作る各音は基本的に「 f ・ mf 」になるのです。
しかし、このフレーズは全体を通してオクターブの2つの音で作られていますから、第2フレーズの和音音形(しかもラスゲァードのような強烈な弾き方)と比べた場合、自動的に「強くない」感じになります。
テキスト以外の楽譜を使う場合にはそうしたことに注意をしましょう。
楽譜に書いてある曲想の記号が p (ピアノ)であっても、それはトータルの響きでそう感じさせるように弾くことが要求されているのであって、そのフレーズの1音1音の大きさを意味しているわけではないのです。
もしこのタンゴに曲想を書き込むとしたら、第1フレーズは mp 、第2フレーズは f となりますが、演奏する場合はどちらのフレーズも各音はほとんど f の音量で弾くということになるのです。
それが「演奏者の意識」であり、そうして弾かれた音楽を聴くと「演奏者の意識」としては「 p ・ f 」のフレーズ表現になっているわけです。
今度はワンフレーズ内の表現について考えてみましょう。「タンゴ」という音楽はどちらかというと官能的な魅力のある曲です。
世俗的といっても良いかもしれません。こうした音楽の場合、フレーズの形(フォルム)は後半がやや軽くなり
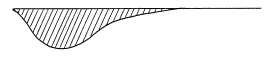
というようになります。
逆にサラバンドやパバーヌといった「宮廷音楽(=一般的に高尚な音楽といえる)」は、割と最後まで充実した響きを維持し
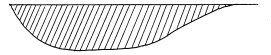
というような形を持つことが多いと言えましょう。
こうしたフォルムを作るには低音と高音のバランスを変えるようにします。
フレーズの前半では低音のテンションを高くし、後半に進むにしたがって、高音にテンションを移してゆきます。
楽譜に書いてある音響記号にしたがってタンゴらしいフォルムを作ってみましょう。
弾弦位置(アタックポジション)を変えて弾く
この曲は同じメロディのフレーズが何度も出てきます。
こうした場合、音量の変化をつけただけではやはり単調さからは脱出できません。
そこで思い切った変化をつけれうために弾弦位置(アタックポジション)を変えて弾くという技術を使います。
こうした手法は弦楽器特有のもので、弾弦位置ヲフレット寄り(弦の中心寄り)で弾くと「柔らかい(=高次倍音の少ない)音」が作られます。
また、ブリッジ寄りで弾くと「輝かしい ・ 固い(=高次倍音の多い)」音が得れます。
こうした技術をヴァイオリンでは「スルタスト(指板の上で弾く) ・ スルポンティチェロ(胸の上で弾く)」と言いますが、ギターの場合は「フレットポジション ・ ブリッジポジション」で弾くと言います。
| フレット寄りのアタックポジション | = [F] = フレットポジション |
| 普通のアタックポジション | = [N] = ノーマルポジション |
| ブリッジ寄りのアタックポジション | = [B] = ブリッジポジション |
アタックポジションを変える技術はフレーズの対比を表現するだけでなく、より色彩的な表現(トーンプログラミング)を行う場合や、クレッシェンドの表現をする場合にも用いられますので、重要な技術と言えます。
ポジションを変えても弦に対する指の角度が変わったりしないように、肘を少しボディから外すフォームをしっかり身に付けましょう。

