27.右手のテクニック(4)
『p 指の正しいフォーム・タッチ・アクション』
ギターの発音を行うのは p i m a という右手の4本の指です。
これらの指が自由に動き、かつ、ギターに対し充分なパワーがかけられるようにするために、基本的なフォームを作ったわけです。といっても、p 指と i m a 指では基本的にフォーム・タッチ・アクションが異なります。
そこでまず p 指のフォーム・タッチについて述べることにしましょう。
写真1を見てください。きちんとしたフォームでギターを弾こうとした際の、自分の視線で見た p 指です。
| 【写真1】 自分の視線 |
【写真2】 正面からのアングル |
【写真3】 横からのアングル |
 |

|  |
p 指は弦に対して45度くらいの角度で構えられます。
それを正面から見た場合が写真2です。鏡に映した時の右手のフォームだと思ってください。
p 指は弦に対してかぶさっています。つまり、押し込むような形になっているということです(ただし、この写真はちょっと p 指が横に出すぎています。見やすくするためです。本来はこんなに横に出ません)。
それに対し、i m a 指は屈曲しているのでPIP関節から先が見えません。
写真3を見てみましょう。
p 指がかぶさっているのに対し、i m a 指は弦をかきあげるようなフォームになっています。だから、p 指と i m a 指とでは、タッチ・アクションが違ってくるのです。
ギターの弦は表面板方向にプッシュされた時、その弦振動のエネルギーはブリッジを通って表面板に伝わり、表面板を震動させることができます。早い話が、大きな良い音がするのです。
そのためには、指の状態は p 指のように押し込むようなフォームであると、大変合理的です。
また、デタッチ(離弦)する時にも、そのまま弦の上をスライドしていけば、ダブルデタッチにならず、ピュアトーンが出しやすいといえましょう。だから、まず p 指で発音の基本をマスターするのです。
こうした発音方法は、『お琴』の発音方法にも共通するものです(「お琴」は正式には『箏』と書くべきかもしれませんが、ここではお琴にします)。
お琴の爪をモデルにして、ギターのタッチ・アクションを考えてみましょう。
お琴には「山田流」「生田流」という2大流派がありますが、その大きな相違点は指にはめる『爪』の形にあります。
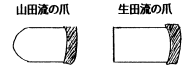
ジャスティ奏法でギターを弾く場合は、デタッチをクリアにするために爪先は鋭角にしますから、生田流の爪とほとんど同じように考えてよいでしょう。
さて、お琴はこの『爪』をはめて演奏しますが、その際、弦を震動させるためのアクション(弾く方向)と爪の起こし具合の関係を『仰角』と呼びます。
そして、この仰角のつけ方によってお琴の音色が作られるのです。
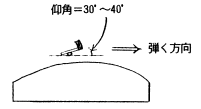
基本的にはこの仰角は30度から40度くらいが良いようです。しかも、弾く方向も「水平方向」と「やや上向き」という変化をつけたりします。
仰角が90度に近いと弦を引っ張りすぎてしまい、ひどい音になってしまいます。また、調律も非常に不安定になるそうです。
逆に0度に近いと音になりません。
つまり、『縦振動と横振動の相違、そしてプッシュの度合い』というジャスティ奏法とほとんど同じ考え方をしているようです。
この考え方を p 指にあてはめてみると、理解しやすいのではないでしょうか。
p 指の正しいタッチ・アクションのあり方は、弦に程よい振動を与え、しかも素早く離弦し、爪の背側で(振動を始めた)弦に接触しないようにするということなのです。
<< 戻る | 「ギタリストへの道」目次 | 次へ >>

